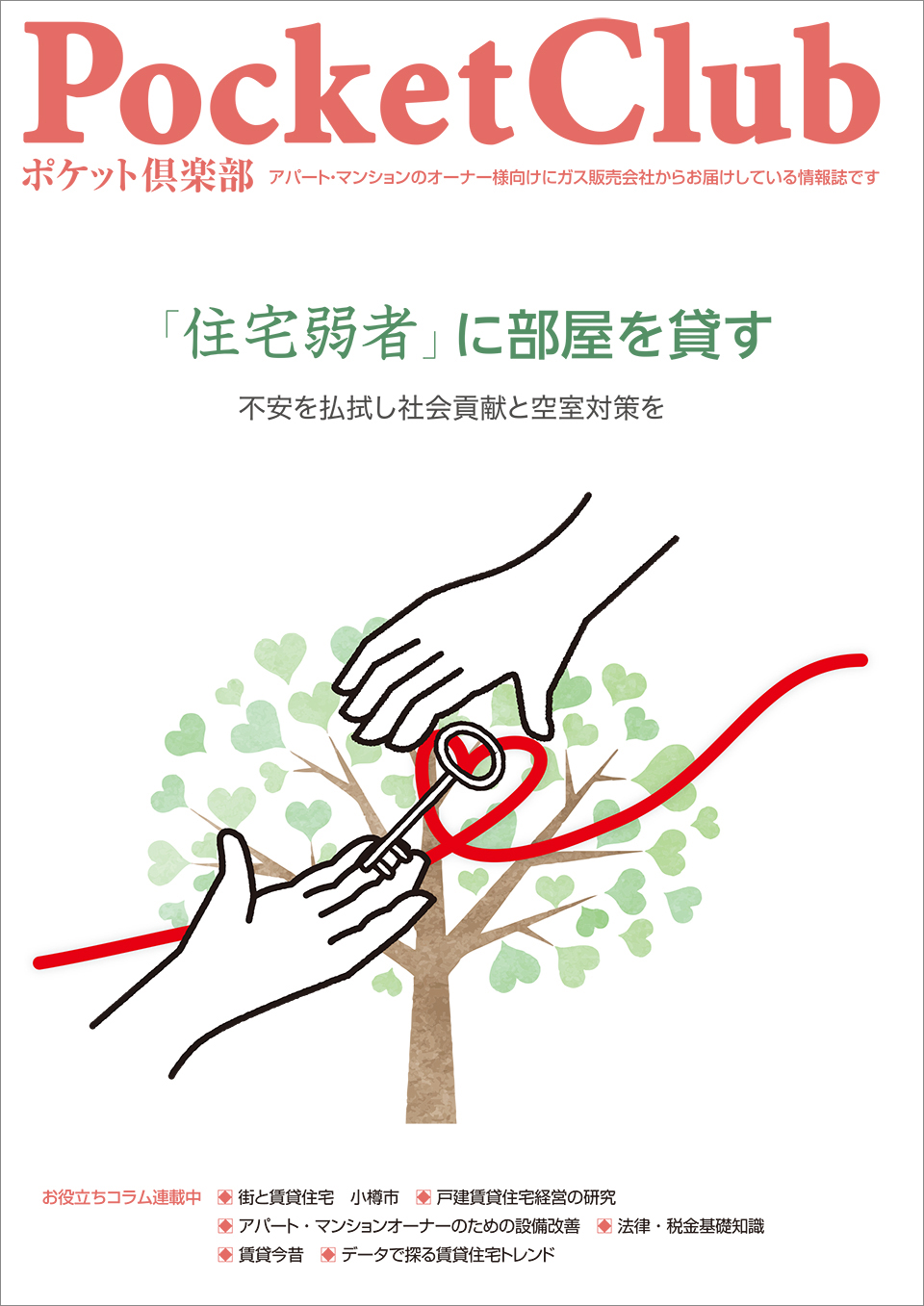賃貸経営ニュースダイジェスト
2026.1.20
賃貸経営ニュースダイジェスト
相続税の調査、実施件数、追徴とも増加
国税庁は、令和6事務年度における相続税の調査等の状況をまとめ、その概要を報告しました。
資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について相続税の実地調査を実施したところ、令和6事務年度においては、実地調査件数は9,512件(対前事務年度⽐111.2%)、追徴税額合計は824億円(対前事務年度⽐112.2%)と、いずれも増加しました。
また、無申告事案については、令和6事務年度において追徴税額が142億円(対前事務年度⽐115.3%)と増加し、公表を始めた平成21事務年度以降で最⾼となりました。
出所・参考
2026年不動産投資トレンド予測、「戸建賃貸」の存在感の高まる
不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家」は、2025年に実施した各種調査や市場データを基に、「2026年不動産投資トレンド予測」を公開した。2025年は金利上昇や物件価格の高騰を背景に、不動産投資市場が大きな転換期を迎え、投資家の戦略や意識にも変化が表れていると分析している。
トレンドの一つとして挙げたのが、「戸建賃貸」の存在感の高まりである。
同社が実施した『不動産投資に関する意識調査(第24回)』(2025年10月)によると、2024年10月以降に購入された物件種別では、戸建賃貸が43.4%を占めた。これは2025年4月時点から7.4ポイントの上昇であり、金融機関の融資姿勢の厳格化や物件価格の高騰を受け、少額投資が可能な戸建へ資金が流れている状況を示している。
また、「インカムゲイン」よりも「キャピタルゲイン」を重視する動きも強まっている。『収益物件市場動向マンスリーレポート』(2025年11月期)によると、投資用物件価格は全種別で過去最高水準を更新した。一方で利回りは低下傾向にあり、同社は資産価値の維持やインフレ対策を重視する投資姿勢が背景にあると分析している。
賃料については、コスト上昇を背景に「賃上げ」の流れが続く見通しである。『戦略に関する意識調査』(2025年10月)では、所有物件の賃料を引き上げた投資家は24.3%に達した。さらに、生成AIの活用も進んでおり、『AIツールの利用に関する不動産投資家アンケート』(2025年8月)では、投資家の42.0%がAIを利用しているとされた。
同社は、2026年は市場参加者の入れ替わりが進み、既存投資家の静観や売却が増える一方で、新規参入の機会も生まれる年になると指摘している。
出所・参考
三菱地所ハウスネット、不動産価格の地域差を可視化
三菱地所ハウスネットは、東京大学の山崎俊彦教授ら(山崎研究室)と共同で実施した「地域ごとの不動産価格を形成する要因分析」に関する研究成果を、国際学会で発表しました。地域特性の可視化により、納得感と透明性の高い不動産査定の実現を目指します。
従来の不動産査定は一律の評価項目に基づいて算出されており、地域特性の反映は営業担当者の知識や経験に依存する傾向がありました。今回の共同研究は、山崎研究室の過去の研究で明らかになった「不動産価格に影響する要因には明確な地域差がある」という知見を社会に実装することを目的に開始されたものです。
研究では、東京都港区における中古マンションの取引データを基に、エリア単位で価格予測モデルを構築しました。機械学習モデルとAI技術を組み合わせた独自の評価手法により、エリアごとの価格影響要因の違いを明らかにしています。港区全体と湾岸地域では影響要因が異なるなどの分析結果が得られ、地域特性を可視化したデータに基づく査定の可能性が示されました。
研究成果をまとめた論文は、マレーシアで開催された国際会議「ACM Multimedia Asia 2025」のワークショップで発表されました。同社は今後、研究対象を他の地域にも拡大し、より納得度と透明性の高い不動産査定のあり方を検討していく方針です。
出所・参考
シニア賃貸の普及拡大と、居住サポート住宅の導入普及
65歳以上の部屋探し専門の賃貸情報サイトを運営するR65不動産、シニア向け暮らしサポートサービスを展開するMIKAWAYA21、居住支援法人あんどは、拡大が見込まれるシニア向け賃貸住宅ニーズへの対応を目的に業務提携しました。この提携により、居住サポート住宅制度を中核に据えた新たなシニア賃貸モデルを構築し、賃貸不動産市場と居住支援制度、地域ケアを横断した市場形成を目指すとしています。
日本では人口減少が進む一方、75歳以上の高齢者人口は増加傾向にあり、2030年には単身高齢者世帯が約800万世帯に達すると見込まれています。しかし、賃貸住宅市場では、孤独死や緊急時対応への不安、老朽賃貸住宅の空室増加、シニア向け住宅の選択肢不足といった構造的課題が存在します。この結果、住み慣れた賃貸住宅での居住継続を望む高齢者と、受け入れに慎重な賃貸市場との間にギャップが生じています。
こうした課題への対応策として注目されているのが、住宅セーフティネット法改正により創設された「居住サポート住宅」制度です。
今回の提携において、R65不動産は賃貸管理会社やオーナーを対象に、シニア対応賃貸モデルの提案や物件情報の発信を行います。MIKAWAYA21は、シニア向け賃貸住宅の建築・改修に加え、生活支援と見守りを組み合わせた住環境モデルを展開します。居住支援法人あんどは、法定居住支援業務の実装や事業基盤強化を通じて、居住支援の担い手拡充を図ります。3社はそれぞれの機能を連携させ、シニア賃貸市場の持続的な普及拡大を目指しています。
出所・参考
国土交通省、「不動産情報ライブラリ」に災害履歴データなどを追加
国土交通省は2025年12月17日、不動産関連情報のオープンデータサービス「不動産情報ライブラリ」に、新たに災害履歴データを追加したと発表しました。これにより、過去に発生した水害・土砂災害・地震災害について、災害種別や発生時期・分布状況を取りまとめた「災害履歴」を誰でも地図上で簡単に確認できるようになりました。さらに、APIでの提供も開始しています。
災害履歴データは、国土調査の一環として実施されている土地分類基本調査(土地履歴調査)の成果をもとに整備されたもので、災害の分布状況を可視化するものです。利用者は地価公示、都市計画、防災情報(ハザードマップ)などのデータと重ね合わせて表示することができます。
加えて、地価公示や都道府県地価調査の地点について、Googleマップでの閲覧が容易になる新機能も追加されました。これにより、利用者は各地点の位置情報を視覚的に確認できるようになり、利便性が向上しています。
「不動産情報ライブラリ」は不動産に関する多様なオープンデータを地図上で重ね合わせて表示できるサービスで、2024年4月に運用を開始しました。官民のシステムやサービスとの連携も進められており、不動産取引の円滑化や新たなサービス創出に活用されています。
出所・参考
2026.1.5
賃貸経営ニュースダイジェスト
2026年の景気見通し、企業の4割超が「踊り場」と回答
帝国データバンクが12月22日に発表した「2026年の景気見通しに対する企業の意識調査」によりますと、2026年の景気を巡る企業の見方で最も多かったのは「踊り場局面」で43.0%でした。一方、「回復局面」と予想する企業は11.0%で、前年より3.3ポイント増加し、2年ぶりに10%を超えました。
逆に、「悪化局面」と見込む企業は17.4%となり、前年から6.5ポイント低下し、4年ぶりに2割を下回る水準となりました。調査対象企業の中には「高市政権が改革を進めれば景気回復につながる」といった期待の声があった一方、「好景気実感は一部に限られる」との慎重な意見も聞かれました。
業種別で見ると、「回復局面」と答えた割合が最も高かったのは「金融」で12.7%、次いで「サービス」「製造・小売」などが続き、「運輸・倉庫」は9.0%と比較的低い結果でした。悪化局面では「小売」が最も高く23.3%、「不動産」も18.8%となっています。
また、2026年の景気に対する懸念材料としては「物価上昇(インフレ)」が45.8%で最多となり、前年から大きく上昇しました。続いて「人手不足」「原油・素材価格の上昇」「為替(円安)」などが挙げられており、企業の先行き不透明感が根強いことがうかがえました。
出所・参考
LIVING & DESIGN 2026、2月4日〜6日 東京ビッグサイトで開催
住宅やインテリア関連の最新トレンドを紹介する国際見本市 「LIVING & DESIGN 2026」 が、2026年2月4日から6日までの3日間、東京都江東区の 東京ビッグサイト 西展示棟で開催されます。 本展示会は、住空間・インテリア・建材・住宅設備など幅広い商品とサービスを一堂に集めた業界向けイベントです。
会期中は、同時開催として、日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」や、暮らし方と住まいのデザインを提案する「LIFE×DESIGN」などが併催されます。
出所・参考
豪雨災害等への緊急対策を支援で45億円配分
国土交通省は12月4日、令和7年度第3回となる「防災・減災対策等強化事業推進費」の予算配分を決定しました。今回、国および地方公共団体が実施する29件の公共事業に対し、合計で45億円の国費を配分します。
「防災・減災対策等強化事業推進費」は、近年激甚化・頻発化している自然災害から国民の安全・安心を確保することを目的とした予算です。今回配分される資金は、洪水・浸水対策、崖崩れ防止、道路・海上交通の安全対策、落雷対策、防災インフラ整備などに充てられます。
出所・参考
11月分消費者物価指数、前年同月比は2.9%の上昇
総務省統計局が12月19日に公表した2025(令和7)年11月分の消費者物価指数は、総合指数で前年同月比が2.9%の上昇。2020年を100として113.2で、前月比(季節調整値)は0.4%の上昇となりました。
今回の総合指数は、2020年を100とした場合、生鮮食品を除くと112.5、生鮮食品とエネルギーを除くと111.6となっています。
出所・参考
11月の新設住宅着工戸数は前年同月比8.5%減、再び減少へ
国土交通省が12月25日に発表した11月の新設住宅着工戸数は59,524戸で、前年同月比8.5%減、先月の増加から再びの減少となりました。着工床面積も4,673千㎡、前年同月比8.5%減で再びの減少。季節調整済年率換算値は718千戸、前月比10.6%減で3か月ぶりの減少となりました。
持家は17,901戸で前年同月比9.5%減、8か月連続の減少。貸家は25,253戸で前年同月比4.2%増、5.5%減,先月の増加から再びの減少。公的資金による貸家は増加しましたが(5.8%増)、民間資金による貸家が減少したため、貸家全体で減少となりました。
出所・参考
既存住宅販売量指数 令和7年9月分、全国において前月比4.9%増加
国土交通省が12月26日に公表した「既存住宅販売量指数(試験運用)」によると、直近の令和7年9月分の既存住宅販売量指数(戸建・マンション合計)は、2010年平均を100とした場合、全国で128.7(合計・季節調整値)で前月比4.9%の増加となりました。
30㎡未満除く合計・季節調整値は前月比3.8%増の116.8。戸建住宅の季節調整値は前月比4.1%増の125.0、マンションの季節調整値は前月比6.7%増の132.3、30㎡未満除くマンションの季節調整値は前月比4.7%増の106.6となりました。
出所・参考
2025.12.20
賃貸経営ニュースダイジェスト
大家さん・不動産事業者のための外国人受入れセミナー
日本賃貸住宅管理協会は、国土交通省補助事業として、「外国人の入居受入れサポートオンラインセミナー」を年明け後、令和8年1月23日(金)と令和8年2月12日(木)に開催します。セミナーはZoomのウェビナーを使用してLIVE配信で行われます。
出所・参考
孤独死対策、単身者向け安否確認支援サービスを開発
放送・通信に携わる事業者のソリューションプロバイダ、シンクレイヤは、AI・Wi-Fiセンシング技術ベンチャー企業のai6と協業し、Wi-Fiセンシング技術を活用した単身者向け居住者安否確認支援サービス「でんぱでみてるくん」を開発しました。このサービスは、居住者の在室状況を可視化し、一定期間動きが確認できない場合は管理者へ通知。カメラやウェアラブル機器を必要とせず、居住者の在室状況を把握できるため、プライバシーを守りながら孤独死という社会課題の解決に貢献することが期待されます。
出所・参考
70歳からのお部屋探し「エイブルシニアパック」を全国展開
エイブルは、高齢者が部屋探しにおいて抱える不安を解消するためのサービス「エイブルシニアパック」を2025年11月11日(火)より全国のエイブル直営店舗(一部除く)にて販売開始しました。
「エイブルシニアパック」では、エイブルの管理物件の契約者を対象とし、ALSOKが提供する安否確認センサーの設置や、いざという時に通報できる緊急ボタンが付いたコントローラー、救急ペンダントのお渡し、看護師資格等を持つスタッフに24時間健康相談ができるサービスを提供、さらに、他社と提携して展開するその他のサービスも付加されます。一定の条件のもとに保証料が無料となるサービスもあります。これら全てのサービスがセットになった高齢者向けの住まい支援サービスは日本でもほとんどなく、料金についても業界最安水準を目指したと同社はアピールしています。
出所・参考
据置型Wi-Fiルーターの悪質セールスへの注意喚起
国民生活センターは、工事不要で手軽に利用できる「据置型Wi-Fiルーター」について、契約トラブルが増加しているとして注意を呼びかけています。
据置型Wi-Fiルーターは、機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる利便性がある一方、「無料と言われて契約したが実際には料金が発生した」「解約時に高額なルーター本体代金を請求された」「電波状況が悪く、十分に通信できない」といった相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
特に、相談に占める契約当事者のうち、70歳以上の高齢者の割合が増加傾向にあることから、国民生活センターでは、相談事例の特徴を整理するとともに、契約内容や通信環境を十分に確認することなど、消費者に対して注意を促しています。
出所・参考
若年単身者の住まい実態、最寄り駅まで徒歩10分以内が半数以上
不動産情報サービスのアットホームは、一人暮らしをしている、全国の18~29歳の学生・社会人を対象に、現在住んでいる部屋の設備・条件や探し方、重視したことなどについてのアンケート調査“UNDER30”を2013年から定期的に実施しています。
今回の調査では「築年数の平均は約13年」「最寄り駅までの徒歩分数は、学生・社会人ともに半数以上が10分以内」といった結果が出ています。
さらに、私生活から浮かび上がる“UNDER30”の実態として、「節約を意識しているものは『食費』がトップで「住宅費」は1割以下」「学生・社会人ともに約6割が災害に対して不安を感じている」「現在の部屋は、学生70.3%、社会人65.0%が防犯面で安心できる」と回答しています。
出所・参考
国民民主、議員立法「空室税法案」を提出
国民民主党は12月11日、議員立法「非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案」を衆議院に提出しました。
本法案は、都市部を中心に住宅価格の高騰が続く中で、投機的取引を抑制し、住宅供給の正常化を図ることを目的としています。
現在、都市部を中心に住宅価格の高騰が問題となっています。その背景には、一定の地域における住宅需要の高まりに加え、外国人を含む一部の者による投機的取引が過度に行われていることがあります。
こうした状況を踏まえ、住宅価格等高騰地域における問題を是正し、当該地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅供給を促進することが、本法案の目的です。
具体的には、以下の点を骨子としています。
- 非居住住宅税の創設
住宅価格等高騰地域に所在する非居住住宅に対し、市町村が非居住住宅税を課すことを可能とする。 - 超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設
個人、法人が住宅を取得後2年以内に譲渡した場合、その所得に応じて所得税及び住民税、法人税を課すること。 - 政府による実態調査
政府は住宅の投機的取引や非居住住宅保有による住宅供給の減少、住宅の価格及び家賃の高騰の実態に係る調査を行う。
出所・参考
築20年以上でも高満足度 旭化成ホームズが二世帯同居の実態調査
旭化成ホームズのLONGLIFE総合研究所は、二世帯住宅の発売から50周年を迎えたことを機に、「築20年以上二世帯同居のくらしと住まい方の変遷」に関する調査結果を公表しました。調査は、2005年以前に建築された二世帯住宅で同居経験のある子世代・孫世代を対象に実施されたものです。
調査によると、二世帯同居の満足度は築年数にかかわらず高く、築20年以上の住宅においても約9割が「満足」と回答。理由としては、経済面での利点や育児・介護の支援、安心感に加え、「親と過ごす時間を持てている」「親孝行ができている」といった回答が約8割を占めました。
また、築20年以上の二世帯住宅では、親世帯が住まなくなったケースが約6割にのぼりました。親世帯退去後の空間の使い方については、子世帯が自ら活用している割合が71%と最も多く、孫への継承は16%、賃貸としての活用は3%でした。未使用のままとなっている住宅は8%にとどまりました。
子世帯による空間活用の内容を見ると、収納のみでの使用は4%にすぎず、生活全般で使用しているケースが半数を超えました。その内容も、寝室や趣味、在宅ワークなど居室として活用する例が多く、親世帯スペースが柔軟に使われている実態が示されました。
調査は2025年6月27日から7月6日にかけて実施され、有効回答数は728件です。
出所・参考
外国人による空き家購入に懸念強く Webguruが意識調査
Webマーケティングやデジタル施策の企画・運営、各種調査・分析などを手がけるWebguru合同会社は、全国的な人口減少や高齢化、大都市への一極集中の進行により深刻化する空き家問題を背景に、外国人による日本の空き家購入に対する意識調査を実施し、その結果を公表しました。
調査結果によると、外国人が空き家を購入することについて、「投機目的で放置されるのではないか」「適切に管理されず、治安や景観が悪化するのではないか」といった懸念が多く挙がりました。また、生活習慣や地域のルール、マナーの違いにより、地域コミュニティの調和が損なわれることを不安視する声もみられました。
安全面に関する懸念も多く、「外国人所有の空き家がトラブルの原因になるのではないか」「人口減少で脆弱になっている地方コミュニティがさらに不安定化するのではないか」との回答が寄せられました。あわせて、先祖代々受け継がれてきた土地や家屋を外国人に託すことへの抵抗感など、情緒的な理由を挙げる意見もありました。
具体的な回答では、空き家を外国人に売却することについて「検討もしたくない」と回答した人が43.6%と最も多く、「日本人を優先する」は30.7%でした。
外国人による空き家所有については、「日本にとって良くない」とする回答が42.9%を占めました。また、自治体による規制については、8割以上が規制強化を支持しました。
出所・参考
シニアの7割が住み替え予定なし。「今後の住まい」意識調査
リコーリースは65歳以上のシニア世代とその子世代(40~59歳)、計861名を対象にシニア世代の「今後の住まい」に関するアンケート調査を実施しました。
シニア世代の意識としては、今後の住まいについて「住み替えるつもりはない」と回答した方が73.0%と最多、住み替え検討者が希望する住居形態は「持家(買い替え含む)」が38.8%と最多、子どもと住まいについて「話をしたことがないが、機会があれば話したい」が26.5%、「今後も話す予定はない」が31.6%と、十分な対話ができていない状況が明らかになっています。一方、子世代の回答からも、親との話し合いは「話をしたことがないが、機会があれば話したい」が25.5%、「今後も話す予定はない」が26.0%と、十分な対話ができていない状況が裏づけられます。
同社は、シニア向け賃貸住宅「アンジュプレイス」を提供しています。