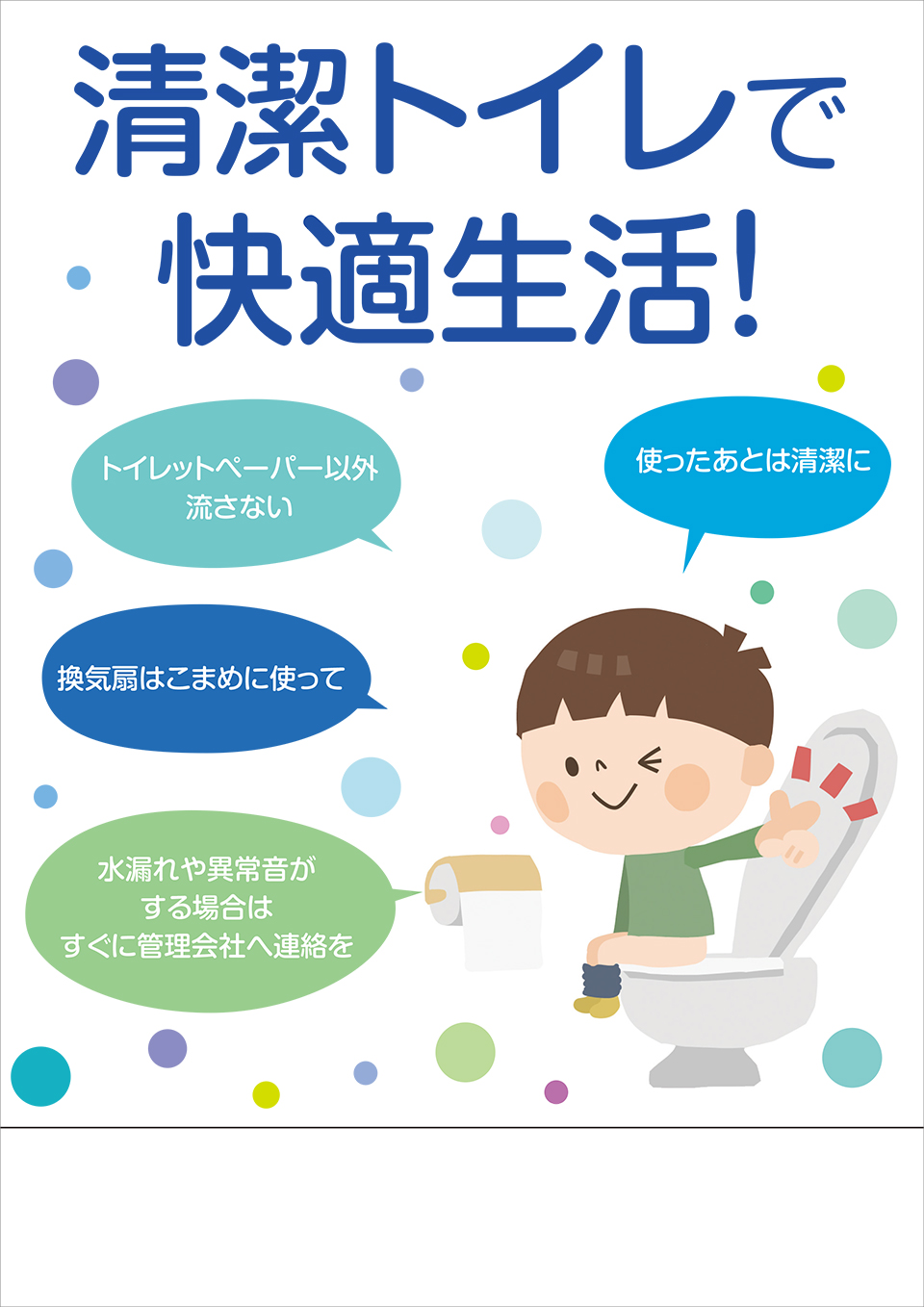ポケット倶楽部
最新号 2026.1.25発行
特集
「住宅弱者」に部屋を貸す
不安を払拭し 社会貢献と空室対策を
高齢者や低額所得者など、いわゆる「住宅弱者」に部屋を貸すことは、社会貢献につながるだけでなく、空室対策や補助金の活用などオーナーにとって多くのメリットがあります。しかし、家賃滞納やトラブルに対する不安から、「貸し渋り」が起こっていることもまた事実です。今回はこれらの懸念を軽減するための公的支援制度について見ていきましょう。

POINT 今後の住宅需要を見据え、「住宅弱者」の受け入れが空室対策になる可能性を検討する
- 「住宅弱者」に向けた支援策や補助金制度について理解を深める
- 物件の状況を見極め、社会貢献につながる賃貸経営を目指す
現状「貸し渋り」の深刻化と賃貸住宅への公的支援
オーナーの誰もが懸念や不安を持っている
「住宅弱者」とは、自身が住む家を見つけるのに困難を抱えている人のことです。正式には「住宅確保要配慮者」といい、法律や省令では、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子ども(高校生相当まで)を養育している者、外国人などが対象になります。自治体の判断で対象を追加することもでき、「新婚世帯」を加えている地域もあります。
令和3年度(2021年度)の国土交通省の調査資料によると、「住宅弱者」の入居に対して、賃借人(大家等)の一定割合が拒否感を持っているというアンケート結果が出ています。高齢者・障がい者に対しては約7割、子育て世帯に対しては約2割、外国人に対しては約6 割がなんらかの拒否感を抱いており、いわゆる「貸し渋り」現象が起こっているようです。
特に、高齢者の場合、最も該当する「入居制限の理由」を聞いたところ、「居室内での死亡事故等に対する不安」が90.9%と圧倒的に高い数値となっていました。「高齢の入居希望者を受け入れたいが保証人がいないし、孤独死などが心配」「低額所得者は家賃を滞納しないか不安」と、オーナーの誰もが懸念や不安を持っているという現状が浮き彫りになりました。
賃貸住宅の空き家・空き室をセーフティネット住宅として活用
また、近年「住宅弱者」の住まいの選択肢をより狭めているのが、公営住宅の老朽化や物件数の減少です。本来、「住宅弱者」のための施策の根幹となるのが公営住宅ですが、すでにある公営住宅は応募倍率が高く、必要とする世帯に行き渡っていません。老朽化や利便性の悪さから十分に活用されていない物件も見られます。さらに人口減などの影響により、公営住宅の数は2005年をピークに減少。今後の公営住宅の増加も期待できないのが現状です。
そうなってくると、活用が期待されるのが民間の賃貸住宅であり、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用し、「住宅弱者」が賃貸住宅に円滑に入居できるための環境整備を推進することを目的とした「住宅セーフティネット法」が2007 年に制定されるに至りました。「住宅弱者」と賃貸住宅の空き家・空き室を持っている賃貸オーナーをつなぐ制度であるこの法律は2017 年に大幅改正され、また直近の改正は昨年2025年10月1日から施行されました。
One Point Interview
地域貢献と収益の両立
空き家再生で新たな賃貸経営を
全国で増え続ける空き家を再生し、賃貸住宅として活用する事業を展開する株式会社ヤモリ。独自のクラウドシステムとデータ活用により、これまで手付かずだった中古不動産市場に新たな可能性を切り開いている同社藤澤正太郎社長に、アパートオーナーが取り組める空き家活用ビジネスについて伺いました。
株式会社ヤモリ
代表取締役 藤澤 正太郎 氏

個人では難しい中古物件市場に新たな仕組み
―― まず、貴社・ヤモリの空き家再生事業の概要を教えてください。
藤澤 当社は2019年の創業以来、空き家をはじめとする未活用の不動産を活性化する事業に取り組んでいます。現在、全国で900万戸もの空き家がありますが、なかなか流通しません。その理由は、ヒト、モノ、カネがないからです。中古住宅を取り扱って再生しようという事業者は個人オーナーか買取再販業者に限られ、大手プレイヤーが入ってきていない。また物件情報が整っておらず、金融機関も耐用年数を超えた中古物件への融資に慎重です。
そこで私たちは3つの事業を展開しています。1つ目は個人オーナーを育成するプラットフォーム事業、2つ目が空き家再生賃貸事業、そして3つ目が入居者向けの見守りIoT事業です。創業以来、不動産取得からリフォーム、管理・運営まですべて一括でできるクラウドシステムを開発し、そこに集めたデータやオーナー情報を活用して、AIも組み合わせながら不動産の再生事業を推進しています。
なかでも「ヤモリの家庭教師」というサービスでは、不動産投資初心者の方に対して、物件探しから購入、運営、トラブル対応まで個別にサポートしています。月額6,900円で専門家に相談できる体制を整えており、これまで3,000名ほどの有料会員をサポートしてきました。会員の物件購入金額は累計130億円以上に達し、平均総事業費の利回りは19%と高い水準を実現しています。このように、知識がない方でも安心して始められる仕組みをつくっています。
当社のミッションは「不動産の民主化」です。不動産所有・賃貸経営をより多くの人に開かれたものにすることを目指しています。これまで中古不動産は情報の非対称性が大きく、一部の専門家だけが収益を上げられる世界でした。しかし、システムとデータを活用することで、個人の方でも適切な判断ができる環境を整えています。知識やノウハウを身につけていただき、長期的な視点で資産形成できる。それが私たちの目指す姿です。
街と賃貸住宅
海の香りとレトロな景色が残る場所
小樽市(北海道)
広大な北海道の西部中央に位置する港湾都市・小樽市。アイヌ語で“砂浜の中を流れる川”を意味する「オタ・オル・ナイ」が地名の由来(諸説あり)とされ、小樽運河をはじめレトロな街並みや建造物が数多く残っています。札幌市から鉄道で約30分というアクセスのよさも魅力で、食や買い物、散策が楽しめる観光地として人気が高い街です。

どんな街?
 江戸時代末期にはニシン漁で栄え、明治時代には北海道開拓の玄関口として重要な港町へと発展した小樽市。1880年、石炭輸送を目的とした幌内鉄道の開通により、北海道で最初の鉄道とともに物流の拠点となりました。昭和初期にかけては、鉄道・海運・商業の要地として発展し、北海道随一の商都として知られるようになります。
江戸時代末期にはニシン漁で栄え、明治時代には北海道開拓の玄関口として重要な港町へと発展した小樽市。1880年、石炭輸送を目的とした幌内鉄道の開通により、北海道で最初の鉄道とともに物流の拠点となりました。昭和初期にかけては、鉄道・海運・商業の要地として発展し、北海道随一の商都として知られるようになります。
1922年、札幌市を含む5市と同時に市制が施行され、2022年に市制施行100年を迎えました。作家・小林多喜二が随筆『故里の顔』で小樽を「北海道の心臓みたいな都会」と記したように、港を中心にヒトやモノが行き来していたのです。こうした流れのなかで金融や商業が発達し、街は大きな繁栄を遂げます。現在も市内には銀行建築や洋風建築が数多く残り、往時の面影とともに、小樽が歩んできた歴史の厚みを感じさせてくれます。
戸建賃貸住宅経営の研究
戸建賃貸のターゲット・ファミリー層
賃貸経営においては、ターゲットを明確にすることが成功の鍵です。戸建賃貸のメインターゲットは、なんといっても子育て世帯です。集合住宅では避けられない「音」の問題や、ライフステージの変化に応じた住み替えニーズに応えることで、長期入居と安定経営が実現できます。
ファミリーの悩みは「音」
ある管理会社での事例です。アパートの1階入居者が脳腫瘍の手術を受け、術後は自宅で安静にしなければなりませんでした。しかし、その真上の2階には3歳の子どもがいる家族が住んでおり、子どもが元気に走り回る音が響いていました。
1階の入居者から「静かにするよう申し入れてほしい」と依頼があり、管理会社の担当者が2階に伝えると、ご夫婦は平謝り。しかし、子どもの行動を完全に制限することは難しく、ご夫婦も弱ってしまいました。幸いにもオーナーが複数の物件を持っており、………本文の続きを読む
アパート・マンションオーナーのための設備改善
トイレ改善で清潔感と快適性をアップ
古いトイレは入居希望者の印象を大きく下げてしまいます。特にトイレは毎日使用する設備であり、清潔感や機能性が不十分ですと入居者の満足度に直接影響します。節水や衛生機能を備えた改善で、空室対策、快適性向上の両方を狙うことが可能です。節水型トイレ、温水洗浄便座の導入、タンクレス化、自動洗浄機能での清掃性向上、床材や壁紙の更新による見た目の清潔感アップなど、効果的な改善を。
所有物件 機能性重視で「入居率向上と管理負担軽減」を目指す
清潔感と利便性を両立した改善
賃貸物件でのトイレ改善は、空室対策、家賃維持、競合との差別化、入居者ニーズへの対応が主な目的となります。対象設備の交換・追加・部分改修で印象を良くし、利便性向上を狙うのが基本方針です。
改善にかかるコストの目安は内容に応じて5万~120万円程度で、仕様や規模により変動します。温水洗浄便座の交換なら5万~15万円、便器本体の交換なら20万~50万円、床材、壁紙を含む全面改修なら………本文の続きを読む
※「清潔トイレで快適生活!」の画像をクリックすると、ポスターをダウンロードできます。ぜひご活用ください。
賃貸経営と法律
契約中の修繕ルール
修繕義務と負担範囲を明確に
貸主と借主の修繕義務の基本
賃貸借契約において、民法は貸主が「賃借物の使用及び収益に必要な修繕をする義務」を規定していますが、これはあくまで原則です。実務では、契約書で負担範囲を具体的に定め、貸主の過剰な修繕義務を避けることが重要であり、電球の交換、蛇口のパッキン交換、ふすま・障子の張り替えなど、入居者が容易にかつ安価に行える程度のものについては借主負担と定められていることが通常です。
特約で借主に通常以上の負担を課す場合には、………本文の続きを読む
賃貸経営と税金
賃貸経営引き継ぎの実務
スケジュール管理
賃貸経営を家族に引き継ぐ場合、相続と生前贈与のどちらを選ぶかで、税金や手続きの内容が異なります。税額計算や特例の詳細は過去回で解説した通りですが、引き継ぎを円滑に進めるには、税務面だけでなく実務スケジュールを管理することが重要です。
相続登記は3年以内
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生を知った日から3年以内に登記をしないと過料が科される可能性があります。遺産分割がまとまらない場合でも、いったん法定相続人全員の共有名義で登記するなど、期限内申請の方法があります。期限を過ぎると登記ができないわけではありませんが、………本文の続きを読む
データで探る賃貸住宅トレンド
マンション家賃高騰でアパート回帰!?
日本経済新聞は「『マンションよりアパート派』増加」と、賃貸アパートへの関心が高まっていると報じました(2025年10月8日付)。マンション賃料の急激な上昇を背景に、都心部でアパートへの注目が高まっているというものです。ただし、さまざまな情報を総合すると、地方では空室率の改善は限定的で、アパート回帰は都心部固有の現象と言えそうです。
都心部でアパート需要が急増
日本経済新聞によると、不動産情報サービスのアットホームの集計では、東京23区で一人暮らし向け(専有面積30平方メートル以下)アパートの1物件あたりの問い合わせ数は2025年7月時点で前年から58%増加しました。これは同条件のマンション(25%増)を………本文の続きを読む
新米大家さんとベテラン大家さん
希少価値を売りにする?
畳の今・昔
畳の部屋はコストがかかる
- 新米
- 知り合いの古いアパートを見に行ったら、畳の部屋がありました。今どき珍しいな、と。
- 大屋
- 畳そのものは日本独自の発展を遂げた床材で、畳を部屋全面に敷いて暮らす文化は日本特有だ。しかし、やがて滅びるかもしれない。もう滅びているかな。
- 新米
- その知り合いは、空室だけどフローリングへの改修はしないと言っています。
- 大屋
- ボロアパートなんですか。
- 新米
- そうです、ボロです。どうせあと何年かで解体だから、………本文の続きを読む
お江戸の賃貸住宅事情
江戸の職業訓練
時代劇『鬼平犯科帳』の長谷川平蔵は実在の人物。火付盗賊改役として重罪犯を取り締まるだけでなく、犯罪予備軍となりがちな無宿人(困窮し農村から江戸に流れ無戸籍状態となった者など)に対する職の斡旋なども行う行政官でした。
収容所兼自立支援施設
長谷川平蔵は通称で本名は
ポケにゃんの暮らしのエボリューション!
キーホルダーの進化
雑貨店に、観光地に、そして街ゆく人のカバンに……。気づけばいつも身近にあるといっても過言ではないキーホルダー。どのように生まれ、進化してきたのでしょうか。
日本に息づいていた!? “ぶらさげ文化”
にゃ。キーホルダー(key holder)は直訳すると「鍵を保持するもの」という意味ですが、英語とは少し異なる“和製英語的”な表現です。欧米では、鍵につける小物は「キーリング(key ring)」や「キーチェーン(key chain)」と呼ばれてきました。使われはじめたのは19世紀末~20世紀初頭で、家やロッカーなど“個人で管理する鍵”を持つ生活へ移行した時代と重なります。失くしやすい小さな鍵をまとめるため、実用性を重視した金属製のシンプルなキーリングが普及しましたが、………本文の続きを読む